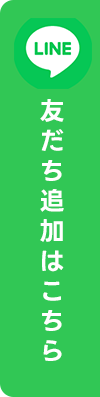シニア犬の熱中症は命に関わる!基礎疾患がある場合の予防策と対処法

「最近、愛犬の元気がないように感じる…」「水を飲む量が減っているような気がする…」と心配になったことはありませんか。
日本の夏は高温多湿で、犬にとって非常に過酷な環境です。特にシニア犬は体力や体温調節機能が低下しているため、熱中症を起こしやすく、命に関わるケースも少なくありません。さらに、持病を抱えている犬ではそのリスクが一層高まるため、予防が何よりも大切です。
今回はシニア犬の熱中症について、症状や基礎疾患ごとの注意点、すぐに実践できる予防法、そして万が一の際の応急処置などをご紹介します。
■目次
1.シニア犬が熱中症になりやすい理由と初期症状
2.基礎疾患別:夏場の注意点
3.今日からできる!シニア犬の熱中症予防
4.緊急時の対処法と受診の目安
5.よくある質問(Q&A)
6.まとめ
シニア犬が熱中症になりやすい理由と初期症状
犬がシニア期になると、体にはさまざまな変化が現れます。特に体温を調整する機能は年齢とともに衰えるため、シニア犬は若い犬よりも熱中症にかかりやすく、重症化するリスクも高まります。
若い犬では、暑さを感じたときに涼しい場所へ移動したり、積極的に水を飲んで体温を下げたり、パンティング(口を開けてハアハアする呼吸)で熱を逃がしたりと、自然な行動で体温を調整できます。しかしシニア犬ではこれらの反応が鈍くなり、暑さへの対応が難しくなる傾向があります。
そのため、ちょっとした暑さでも体調を崩しやすく、気づかないうちに熱中症へと進行してしまうことがあります。そこで、実際に熱中症がどのように現れるのか、症状の段階について見ていきましょう。
<軽度の場合>
・激しいパンティング
・動きが鈍い
・歯ぐきや結膜の充血
・体温の上昇
<中度の場合>
・よだれが増える
・元気や食欲の低下
・水を飲まない
・ふらつき
・下痢や嘔吐
<重度の場合>
・粘膜が白または真っ赤になる
・吐血や血便
・痙攣
・意識がもうろうとする
・呼吸困難
これらの症状に気づいたときは、暑さによる体調不良を疑い、早めに動物病院を受診することが大切です。
基礎疾患別:夏場の注意点
シニア犬の中には持病を抱えている子も多く、熱中症予防では以下のような疾患ごとに細やかな配慮が求められます。
<心臓病の場合>
血液循環が不十分になり、体の熱を逃がしにくくなります。そのため、高温多湿での活動や激しい運動は避けましょう。
<腎臓病の場合>
水分バランスを崩しやすく、脱水の危険があります。水を常に飲める環境を整え、飲水量が少ない場合はかかりつけ医に相談してください。
<呼吸器疾患の場合>
パンティングがうまくできず体温が下がりにくいため、冷房で室温を調整しましょう。また、散歩は早朝や夕方などの涼しい時間帯に行い、こまめな水分補給を心がけましょう。
<関節炎や運動制限のある場合>
涼しい場所への移動が難しいため、暑い時間の散歩を避け、室内運動や短時間の散歩にとどめましょう。
今日からできる!シニア犬の熱中症予防
熱中症は屋外だけでなく室内でも起こります。そのため、以下のように生活環境を整えることが何よりも重要です。
<室内での工夫>
エアコンや除湿機で温湿度を管理し、直射日光を遮る工夫をしましょう。また、ベッドは窓際を避け、複数の水飲み場を用意し、自由に水分補給ができる環境を整えてください。冷感マットやひんやりグッズも有効です。
<散歩時の工夫>
散歩は日中を避け、涼しい早朝や夕方に短時間で行いましょう。その際は保冷剤付きのネッククーラーを使ったり、飲み水を持参したりしておくと安心です。また、アスファルトは熱を持ちやすいため、なるべく芝生や土の道を選ぶと良いでしょう。ただし、体調がすぐれない日は無理をせず、散歩を控えることも大切です。
<水分補給の工夫>
器を大きくしたり場所を増やしたりして、いつでもどこでも水分補給ができる環境を整えましょう。あまり水を飲まない犬の場合、市販の水分補給用スープやウェットフードを活用するのもおすすめです。
緊急時の対処法と受診の目安
「熱中症かもしれない」と感じたら、すぐに涼しい場所へ移動させ、首や脇、足の付け根など太い血管が通っている部分を保冷剤や冷たいタオルで冷やしてください。水が飲める状態であれば、少量ずつこまめに与えましょう。
ただし、嫌がったり飲めなかったりする様子がある場合は、無理に与えると誤嚥の危険があるため控えてください。これらの応急処置を済ませたら、すぐに動物病院へ連絡してください。
特に以下のような症状が見られる場合は、緊急性が高いため、注意が必要です。
・動かず、ぐったりしている
・ふらつきや痙攣がある
・嘔吐や下痢を繰り返す
・吐血や血便がある
・舌や歯ぐきなどの粘膜が白っぽい、または真っ赤になっている
また、動物病院へ向かう際には、無理に歩かせずキャリーや車で静かに移動させましょう。移動中も体を冷やし続けることが大切です。なお、症状が急速に悪化することもあるため、「大丈夫かもしれない」と自己判断せず、早めの受診を心がけてください。
よくある質問(Q&A)
Q:熱中症予防は何歳から対策が必要ですか?
熱中症の予防は年齢にかかわらず大切ですが、特に7歳を過ぎてシニア期に入った犬では、体温調節機能が低下するため、注意が必要です。
Q:薬を飲んでいるシニア犬の夏場の注意点は?
基礎疾患がある場合は熱中症のリスクが高まります。室内では適正な室温・湿度を維持して、直射日光が当たらないようにしましょう。また、日頃の体調にも注意しましょう。
Q:エアコンをつけっぱなしでも大丈夫ですか?
問題ありません。ただし、愛犬自身が自由に移動して体温調節できるように、涼しい場所とそうでない場所を選べる環境を用意することが望ましいです。
Q:散歩に行けない日の運動不足解消法は?
室内遊びや知育トイを活用して、運動不足とストレスを防ぎましょう。
Q:水をあまり飲まない犬にはどうすればよいですか?
水の器を大きくしたり、置き場所を増やしたり、風味をつけたりすることで、水を飲むきっかけを増やす工夫ができます。市販のスープなども役立つため、状況に応じて取り入れてみましょう。
まとめ
熱中症は、特にシニア犬にとって命に関わる重大なリスクです。体温調節の機能が衰え、さらに持病がある場合には危険性が一層高まります。
そのため、日々の小さな変化を見逃さず、室内環境の工夫や散歩の時間帯の調整、水分補給の工夫を重ねることで、リスクを大きく減らすことができます。万が一のときには速やかに応急処置を行い、できるだけ早く動物病院を受診することが大切です。
当院では、季節に応じた健康相談や、持病に配慮した生活指導も行っております。愛犬の体調に少しでも不安を感じた際には、どうぞお気軽にご相談ください。
■関連する記事はこちらから
夏の暑さからシニア犬の皮膚を守ろう!|高温多湿と皮膚トラブルは背中合わせ
愛犬を守るために!|犬のお散歩など外出時の熱中症対策について
犬の熱中症対策について|予防法を徹底解説
東京都世田谷区の動物病院なら『つるまき動物病院』
診察についてはこちらから
TEL:03-6413-5781