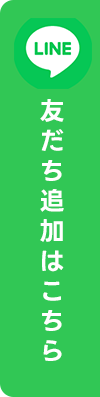シニア猫の腎臓病ケア|秋から冬に気をつけたい体調管理のポイント

「最近、水を飲む量が減った気がする」「寒くなってからトイレの回数が増えている」そんな変化に気づいたことはありませんか?
シニア猫に多い病気のひとつに腎臓病があります。腎臓病はゆっくりと進行するため、初期には目立った症状が出にくく、気づいたときには進行していることも少なくありません。
特に秋から冬への季節の変わり目は、気温や湿度の変化によって体調を崩しやすく、腎臓病の悪化にもつながりやすい時期です。
そこで今回は、シニア猫の腎臓を守るために、飼い主様ができる工夫と病院でのケアについて解説します。
■目次
1.なぜ高齢になると腎臓病のリスクが上がるのか
2.季節の変わり目(秋〜冬)が腎臓に与える負担
3.自宅でできるケア|水分・食事・環境管理
4.見逃してはいけないサイン|早期発見のチェックリスト
5.動物病院での検査と治療の流れ
6.よくある質問(Q&A)
7.まとめ
なぜ高齢になると腎臓病のリスクが上がるのか
腎臓は、体の老廃物を尿として排出したり、水分やミネラルのバランスを保ったりする大切な臓器です。ところが、腎臓の細胞は一度壊れると再生しにくいため、年齢とともに少しずつ機能が低下していきます。
そのため、シニア猫(7歳以上)になると腎臓病のリスクが一気に高まるといわれています。
さらに猫は体調の変化を隠す性質があるため、飼い主様が気づいたときにはすでに進行しているケースも多いのです。
慢性腎臓病についてより詳しく知りたい方はこちら
急性腎不全についてより詳しく知りたい方はこちら
季節の変わり目(秋〜冬)が腎臓に与える負担
秋から冬にかけては、腎臓病を悪化させる要因がいくつも重なります。
・気温が下がると水をあまり飲まなくなる
・空気の乾燥で脱水が進みやすい
・寒さによる血流の低下で腎臓の働きが落ちる
・運動量が減り代謝が下がる
このように、秋から冬は「腎臓に負担をかけやすい季節」なのです。「ただの季節変化」と見過ごさず、小さな変化に敏感になることが大切です。
自宅でできるケア|水分・食事・環境管理
愛猫の腎臓を守るためには、日常のちょっとした工夫がとても大切です。
〈水分摂取を工夫する〉
猫はもともと水をあまり飲まない動物です。特に寒い季節は飲水量が減りやすいため、以下のような工夫が必要です。
・お皿を複数箇所に置いてみる
・流水タイプの給水器を使う
・フードにぬるま湯をかけて香りを立たせる
・ウェットフードやスープ仕立てのフードを取り入れる
自然に水分をとれるようにしてあげることで、腎臓への負担を減らすことができます。
〈食事管理〉
腎臓病の猫には、獣医師から「腎臓ケア用フード」が勧められることがあります。
ただし、一番の問題は「食べないこと」です。ドライとウェットを組み合わせたり、好みに合わせて工夫することで食欲を維持することが大切です。
〈室内環境の調整〉
寒さや乾燥は腎臓に負担をかけます。そこで、室内環境を整える際は次のようなポイントを意識すると安心です。
・室温は20℃前後を目安に
・加湿器で湿度を40~60%に保つ
・風の当たらない場所に暖かい寝床を用意する
「快適に過ごせる環境」を整えることも立派な腎臓ケアです。
見逃してはいけないサイン|早期発見のチェックリスト
腎臓病は初期症状が分かりにくいため、日常のちょっとした変化に気づくことが大切です。
〈注意したい体調の変化〉
・水をよく飲むのに体重が減る
・尿の量が極端に増える、または減る
・嘔吐や下痢が続く
・食欲が落ちる
・毛並みがパサつき、艶がなくなる
これらは腎臓病のサインである可能性があります。
〈緊急受診が必要な症状〉
・ご飯をまったく食べない
・水も飲まない
・尿がまったく出ない
・ぐったりして動かない
こうした症状は命に関わる危険な状態です。見られた場合は迷わず、すぐに動物病院へご連絡ください。
動物病院での検査と治療の流れ
腎臓病は、何よりも早期に見つけることが大切です。特にシニア猫では、たとえ元気そうに見えても半年に1回は血液検査を受けておくと安心です。すでに腎臓病と診断されている場合は、3か月ごとの定期検査が望ましいでしょう。
血液検査や尿検査を通じて腎臓の働き具合を確認し、その結果に基づいて治療方針を調整していきます。
〈治療方法の一例〉
腎臓病の治療にはいくつかの選択肢があります。
・点滴治療(皮下輸液など)で脱水を防ぐ
・薬を使って血圧やリンのコントロールを行う
・腎臓ケアフードを取り入れて負担を軽減する
こうした治療はすべて「その子の状態に合わせた調整」が必要であり、定期的に病院で状態を確認しながら進めていきます。
〈当院の特徴〉
当院では、一般的な治療に加えて「再生医療」を取り入れた新しい選択肢をご提案することも可能です。さらに「今の治療方針で大丈夫かな」と不安を抱える飼い主様に向けて、セカンドオピニオンのご相談も積極的にお受けしています。
「今の治療で本当にいいのか」「他の方法はないのか」と感じたときは、お気軽にご相談ください。
よくある質問(Q&A)
Q: 腎臓病は治りますか?
残念ながら完治は難しい病気ですが、治療とケアで進行を抑え、長く穏やかに過ごすことができます。
Q:水を飲ませる工夫は?
器の数を増やす、ウェットフードを混ぜる、スープ仕立ての食事を与えるなどが効果的です。
Q:どのくらいの頻度で検査が必要ですか?
健康なシニア猫は半年に1回、腎臓病を抱える子は3か月ごとを目安にしてください。
Q:他院で治療中でも相談できますか?
はい、当院ではセカンドオピニオンを承っております。他院で治療中の方もご相談いただけます。
まとめ
シニア猫に多い腎臓病は、秋から冬に悪化しやすい病気です。水分補給や食事管理、快適な生活環境に加え、定期的な検査と早めの治療が何より大切です。
「最近、飲水量や排尿が気になる」「冬に向けて体調を整えておきたい」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。
東京都世田谷区の動物病院なら『つるまき動物病院』
診察についてはこちらから
TEL:03-6413-5781